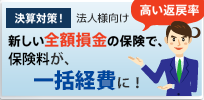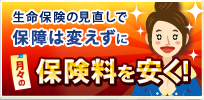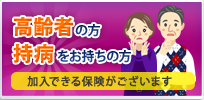大変なことになった・・・
「あの」クレディ・スイスが破綻寸前まで追い込まれた挙げ句、ライバルのUBSに「たった4200億円」で買収されてしまった。
しかも、この買収に伴い、クレディ・スイスが発行した社債(AT1債)がデフォルトするという。
その額、なんと170億ドル。日本円にして2.3兆円。
名門クレディ・スイスが発行する社債。
AT1債という特殊なものであることを割り引いても「かなり安全性は高い」と判断するのが普通で、それがデフォルトするとは到底想像出来ないだろう。
今回のことで、AT1債というものの存在を初めて知ったが、調べてみると、
・劣後債の一種ではあるものの
・金融機関の自己資本に組み入れることが出来る
という、何とも不可思議なものであった。
順を追って説明していきたい。
まず、劣後債とはその名の示す通り
「他の債権より優先順位が『劣り』、支払いも『後』になる」
という特性を持つ社債で、その会社に緊急事態(破綻など)が発生した場合、支払い順位が最も高い一般の社債より後回しにされるが、そのかわり社債より高い利回りを得ることが出来る。
とは言え一応債権ではあるので、株式よりは優先順位は高い。
これが一般的な理解である。
で、AT1債。これがまた相当特殊だ。
AT1の正式名称は「Additional Tier1」
Additional(アディショナル)とは、付加的なとか、追加のという意味で、サッカーの「アディショナルタイム」をイメージすると分かりやすい。
そしてTier1とは、2008年のリーマンショックを契機に制定されたもので、銀行の自己資本を定義するための用語である。(自動車業界にも自動車メーカーに部品を提供する一次サプライヤーをTier1と呼ぶが、これとは関係ない)
あの時、多くの金融機関が大きな痛手を負ったが、その根本的な原因は、
自分の身の丈に合わない大博打を打った
ためである。
平たく言えば、顧客から預かった金に何十倍、何百倍というレバレッジをかけて、高利回りの金融商品に投資をし、それが破綻したわけだ。
そこでリーマンショック後、各銀行が集まって
博打は自分の財産に見合った規模でやりましょうね。
というルールを作る。
まるで高校生か大学生にでも諭すような話だが、敢えてそれを言わねばならぬほど、金融機関のタガが緩んでいたのだ。
BIS(国際決済銀行)という各国の中央銀行があつまる国際組織で、そのルール作りがされた。
それがバーゼルⅢ
バーゼルとはスイスにある都市の一つでBISの本部がある場所。
そこで各国の銀行のお偉いさんが集まって話し合いをすることから、バーゼル合意とかバーゼルⅢ(3回目の大きなルール変更)などとネーミングされている。
このバーゼルⅢでは、銀行の自己資本比率に対して「かなり厳しいルール」が課せられることになり、一般的にBIS規制などとも言われる。
具体的には各銀行に「自己資本比率8%以上」を求め、かつ自己資本の「質」にも高い要求をしている。
このルールには金融機関の「暴走」を防ぐ意図があり、要は、
あんまり無茶な博打はしなさんなよ
ということなのだろう。
ここで重要なものが、先に触れたTier1という考え方だ。
銀行には現金をはじめとして、多種多様な「資産」がある。
その中で、何が自己資本なのか?かつ自己資本の中でも「質」の良いものは何なのか?
それを定義するのがTier1だ。
これに分類されるものは「質の良い自己資本」と見なされる。

自己資本には様々な定義があるが、平たく言えば「自分の金」だ。
少々小難しく言えば「返済義務のない金」とも言い換えられる。
最も代表的な自己資本は株式。
人から出してもらった金(自分で出す場合もあるが)ではあるが、返済義務はない。
次に毎年の利益。
1年間ビジネスを回して得た利益、更にそこから税金を支払った後に残ったお金(税引き後利益)は、これこそ完全に自分のものだ。
そのため、基本的な自己資本は
株式+毎年の利益の蓄積
となる。
これに対して、社債は、
「個人や法人から借りている」
ものであり、返済義務があるから自己資本には含まない。
だが、AT1債はこのTier1のAdditional (追加的な)ということで、Tier1と見なされるため、自己資本扱いとなり、金融機関側にとっては非常に都合が良いのだ。
さて、何故に社債が自己資本なのか?
それは「劣後事由」に該当した場合、お金を返さなくても良いから。
この点、株式的でもある。
AT1債を始めとする劣後債には「この条件に該当した場合には返しませんよ(劣後事由)」というものがあらかじめ設定されており、AT1債の場合、破綻や当局の指示などがその条件となっていた。
つまり、緊急時には「返済義務がない」ということで、自己資本扱いとなるのだそうだ。
このようにAT1債は社債と株の中間のような位置づけで、投資家からすれば「安全な割に高利回り」、発行する金融機関からすれば「自己資本に繰入られる」というのがメリットとなる。
そのため、バーゼルⅢ以降、ヨーロッパの銀行でAT1債の発行が爆発的に増えたのだが、そこには一つ落とし穴が・・・・
先に挙げた「当局の指示」という条件。
あまりに曖昧ではないか?
実際、今回もスイス当局が「クレディスイスのAT1債は無効」と宣言したことで、この条件を満たし、見事デフォルトと相成ったわけだが、こんな一国の恣意的な宣言で債券を紙屑にされてしまっては、投資家もたまったものではない。
また、本件においては、クレディ・スイスがUSBに「買収」されたことで、本来なら劣後債より優先順位が劣るはずの株式が以後も有効である。(もちろん大暴落はしてはいるが)
最もリスキーなはずの株式は保全され、社債がデフォルトを起こすという極めて異常な事態となっている。
結果、現在のAT1債は、額面1ドルが0.03ドルと、97%減という悲惨な状態に。
が、何とこれが「売れている」というのだから驚く。
買い手はヘッジファンド。
その魂胆としては
・クレディスイスとUSBの「結婚」が破談になる可能性
・猛批判を受けて、スイス当局が無価値化を撤回
・AT1債を巡る取扱いで訴訟が起こり、和解案が提示される
というあたりらしいが、まあ、何とも商魂たくましいと言うか、何と言うか・・・・
まるでクレディスイスという死肉にたかるハゲワシのようでもある。
リーマン後のバーゼルⅢ制定や、それをかいくぐるようなAT1債の発明、更には「マズい!!」となるやスイスという国を挙げてデフォルトを起こし、そしてそのゴタゴタをヘッジファンドが狙う。
他の銀行のAT1債も暴落しており、まだまだ混乱が収まる様子はない。
いつか見た光景のような気がするのは私だけだろうか?
本日のコラムでした。
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします