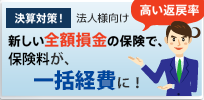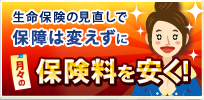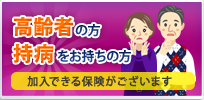法人保険に「福利厚生プラン」というものがあります。
・法人が契約者、社員を被保険者として保険に入る
・保険料の1/2が損金として計上可能
というものですが、法人保険としては、やや仕組みが複雑なため、本日はこれら福利厚生を導入するにあたり、その実務を解説したいと思います。
これから福利厚生プランを導入したい、という方は以下の5つを理解する必要があります。
1 普遍的加入とは?
2 使用商品は「養老保険」に限定!!
3 役員も加入する場合、「保険金」比較で従業員の10倍程度以内
4 積立金はあくまで「会社のもの」
5 従来の福利厚生プランの問題点とは?(変額保険のメリット)
それぞれの項目ごとに説明します。
1 普遍的加入とは?
普遍的加入とは、例えば「入社3年目以降の社員全員」など、公平な加入を意味をします。
「男性社員だけ」とか「課長以上だけ」というような条件では「普遍的」とはなりません。
福利厚生プランを導入する場合、この普遍的加入だけは、厳密に守る必要があります。
なお、一般社員、課長、部長など役職ごとに保険金で「差をつける」ことは「やり過ぎなければ(詳しくは後述)」問題ありませんが、「保険に入る」という加入に関しては公平性が求められます。
国税側からしても、
保険料の半分を損金にするのだから、フェアにやってね。
ということだと思います。
2 使用商品は「養老保険」に限定!!
これは税制上のルールですが、福利厚生プランに使用できる商品は養老保険に限定されています。
養老保険は保障期間が決まっている貯蓄型の保険で、死亡時の保険金と満期時の満期保険金が同額です。
以下に例を挙げます。
例:30歳 男性 65歳満期 500万円養老
死亡時保険金:500万円
保険料:年間5万7,000円
65歳満期時の総支払保険料:199.5万円
65歳満期時の満期保険金:200万円
つまり、保険に加入したことにより、30歳から65歳までの間、仮に死亡(もしくは高度障害状態)した場合には200万円の保障がありますが、無事、65歳を迎えた時には199.5万円の支払に対して、200万円の満期金が用意されます。
死亡しても、満期を迎えても200万円。
これが養老保険です。
福利厚生プランではこの養老保険を使うことが必須条件となります。
3 役員も加入する場合、「保険金」比較で従業員の10倍程度以内

福利厚生プランに加入する場合、実は役員も一緒に入ることが出来ます。
普遍的加入を満たせば、「オマケ」で役員も入れて、その分の保険料も1/2損金になります。
しかし、一般従業員の死亡保険金が200万円の場合、役員も同じで良いかと言えば、それも違います。
実際に死亡した時に、会社に与えるインパクトが全く違うからです。
そのため、前述した通り、役職ごとに保険金を変えたり、もしくは役員だけを一般従業員より高額な保険金を設定することは「良い」とされています。
ただし、「どれくらいの差をつけても良いのか?」という点について、国税から正式な見解はありません。
あくまでケースバイケースですが、「10倍以内程度」という解釈が一般的です。
例えば、こんな形です。
死亡保険金
従業員 200万円
役員 2,000万円
なお、保険屋の中には「ルールがないのだから20倍でも30倍でもOK」というような適当なことを言う方もいますが、実際に税務調査で問題になった時に責任をとれるわけではありません。
実際に否認されたケースはごく少数ではありますが、あまりに内容が経営者サイドに偏っていると、
「福利厚生を装っているが、実態としては経営者のためだけの保険」
というような指摘をされることもあるので、要注意です。
4 積立金はあくまで「会社のもの」
ほぼ貯金のような養老保険を1/2損金で落とせる。(節税効果)
いわば、積立金の一部を税金で助成してくれているようなもので、それが社員や役員の保障や将来の貯蓄になるのです。
しかし、ここで重要なことは、これらの資産は
あくまで会社のもの
ということです。
従業員1人1人の保険ではありますが、契約者は会社であり、保険料を支払っているのも会社です。
そのため、解約する権利や、解約返戻金を受け取る権利は全て会社に帰属します。
これが中退共や確定拠出年金などであれば、その掛金は法人が支払った瞬間、従業員の物となり、法人側からは一切の手出しが出来ません。
その点、福利厚生プランであれば、いざという時には「内部留保」として経営者が自己判断のもとに利用することが出来ます。
資金を自分の手元に置いておける。
実はこの点こそを「最大のメリット」として評価する経営者が多いです。
5 従来の福利厚生プランの問題点とは?
(変額保険のメリット)

しかしこのような福利厚生プランも、最近では「魅力が低下した」という声が少なくありません。
その原因は超低金利。
保険会社の運用のメインを担う10年国債の利回りは0.04%前後と、1億円買っても年間4万円のリターンしかない状態です。
そのような運用環境の悪化に伴い、福利厚生プランで使用される養老保険の返戻率も急降下してしまいました。
保険会社も、お金を預かったところで増やすことが出来ないのです。
そのため、前述したように「35年間で199.5万円支払って、200万円しか戻ってこない」というような養老保険ばかりで、中には逆ザヤ(満期金が支払った金額以下)になってしまうものもあります。
いくら1/2損金だと言っても、大事な会社の資産がほとんど増えない、もしくは減らしてしまう、ということになり、今後のインフレリスクなどを考えると
本当にこのままで良いのか?
と思う経営者が多いのかもしれません。
そこで出てきたのが変額保険です。
変額保険は、支払った保険料を「国内株式」、「海外株式」、「REIT」、「債権」などのファンドに投資をします。投資先は契約者が決めます。
その結果、死亡保険金も、将来の満期金も運用成績次第で上下する、つまり「変わる」ので変額保険です。
但し、保険金だけは「最低保証」があり、加入時の金額より下回ることはありません。
保険金 加入時の金額(例:200万円)は最低保証、運用成績によって上がる可能性がある
満期金 最低保証なし、下がる可能性も上がる可能性もある
保険としての機能は維持しつつも、投資信託のようなファンドで運用できるわけです。
しかも、福利厚生ですから1/2損金です。
1年、2年という短期の場合、資産が増えるか減るかは市場の「ご機嫌」次第であることは否めませんが、10年、20年という長期で見れば、株式市場や不動産市場が拡大を続けていることは、過去の歴史が示しています。
このようなマーケットで会社の資産を運用できることが、変額保険の魅力です。
福利厚生プランならみかづきナビにお任せ下さい!!
福利厚生プランの導入にあたっては、以下のポイントを検討する必要があります。
・従業員と役員の保障バランスをどうするか?
・役員、従業員の保険料バランスは問題ないか?
・会社の売上、利益に対し、保険料は過大ではないか?
・将来の持続可能な制度設計になっているか?
・積立金を退職金規約と連動させるか、それとも非連動の生命保険規定にするか?
・変額保険を採用した場合、どのファンドにどの程度(割合)投資するべきか?
これらの事項の一つ一つを、精査し、更には分野によっては税理士、社労士などとも連携していかないといけません。
みかづきナビなら、豊富な実績に裏付けされた経験により、福利厚生プランの導入を完全サポート致します。
御社にとって無理・無駄のない制度設計をご提供致します。
ご興味をお持ちの方は
info@mikazuki-navi.jp
までご連絡下さい!!
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします